スキルアップ
【連載】自動車開発におけるシミュレーションの基本(第3回)

目次
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。
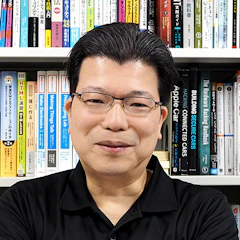












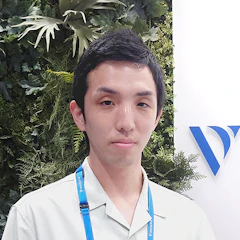


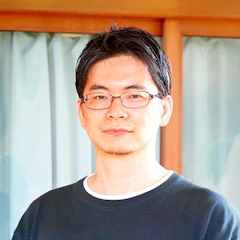



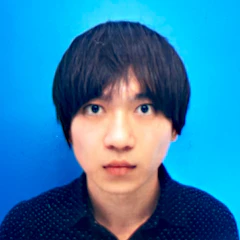


























-portrait.webp)



























イノベーションを加速させる
おすすめ記事

日本企業はどう戦う!? 及川卓也さんが語るデジタル時代の道しるべ

経済産業省「DXレポート」の裏側、国がデジタルで目指す真の未来像とは?

セキュリティ専門家が指南:「危ない! 危ない!」というあおりに踊らされず、自組織の脆弱性を見極めた対処を SBテクノロジー・辻伸弘氏

【連載】冒険者の地図:高卒エンジニアからメガベンチャーのリーダー職に、国内屈指のQAエンジニアに上り詰めた河野哲也さんの逆転人生(前編)
ランキング