ビジネス
プロトタイプにコストをかけず、“ダンボールのニワトリ”を作ろう ambie株式会社・三原良太代表が説くイノベーションの起こし方(前編)

ambie株式会社代表取締役三原良太さん
2010年にソニー入社後、ヘッドマウントディスプレイやBluetoothイヤホンの設計を担当。2017年「ambie sound earcuffs」を開発し、ソニーとWiLのジョイントベンチャーとしてambie株式会社を立ち上げ出向。プロジェクトリーダーとして開発から流通、マーケティングまでを中心となって行い、2020年CEOに就任。
目次
2017年2月、耳の穴を塞がずに音楽を聴くことができるイヤホン「ambie sound earcuffs」を世の中に送り出し、“ながら聴き”というスタイルを定着させた先駆者であるambie株式会社(以下、ambie)。
創業者の三原良太さんは、ソニーのハードウェアエンジニア時代にこの新規事業プロジェクトに携わることとなった。その後、ソニーと投資会社・WiLのジョイントベンチャーとしてambieを立ち上げ、独立した。
これまでに誰も考えつかなかった新しい価値観を作り、マーケットに浸透させていくために、一体どのようなことに取り組んできたのか。また、一人のエンジニアとして、製品開発あるいは製品そのものに対する品質へのこだわりなどを聞いた。
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。








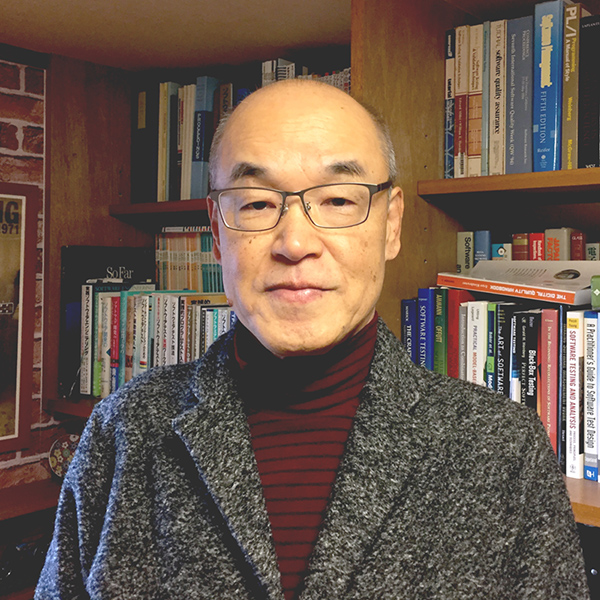
























.png)
































