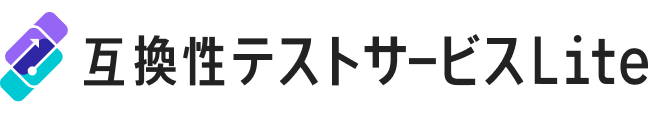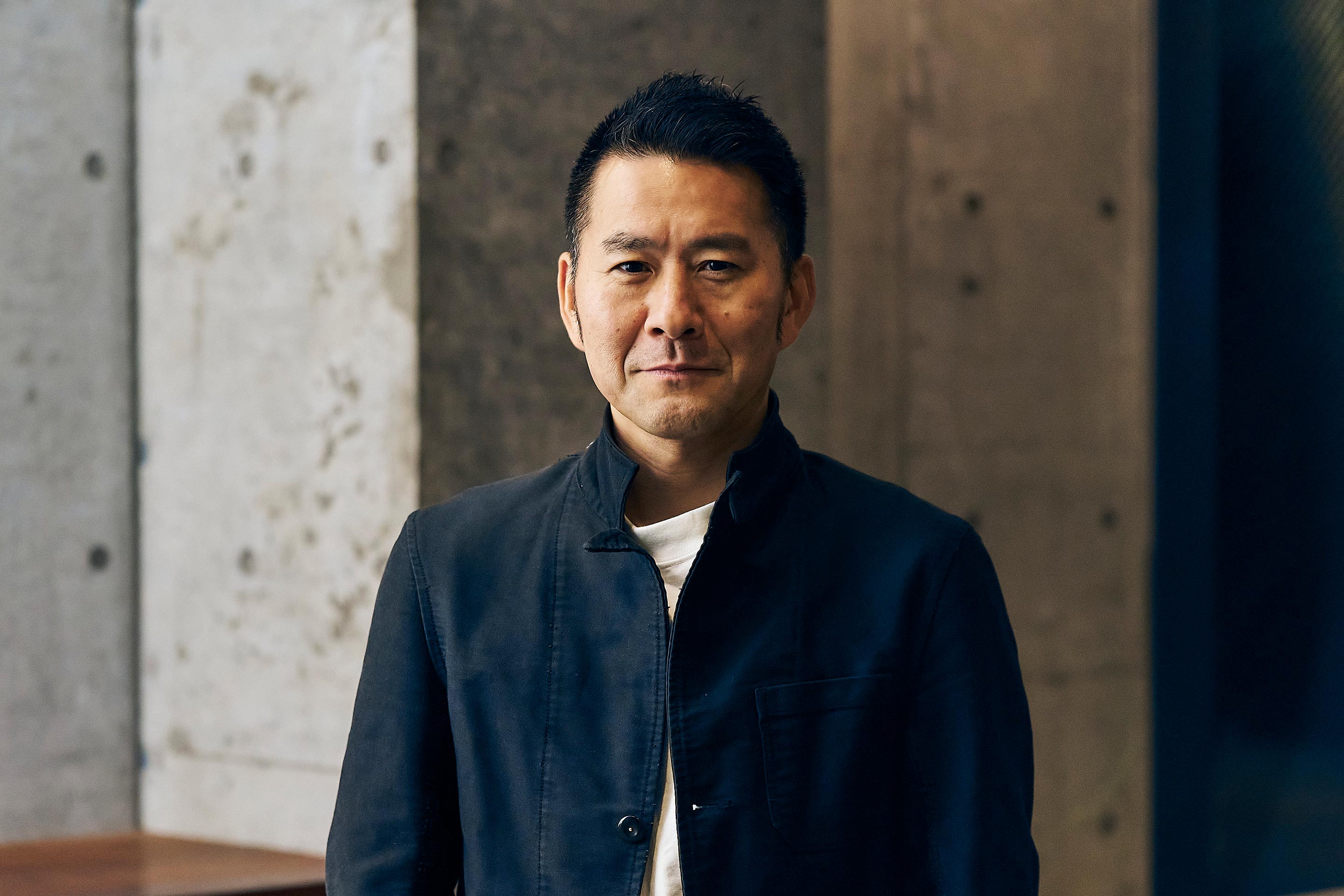ビジネス
【連載】QAの変遷を語る:ベリサーブ・佐々木方規さん「QA・テスト業界の共通言語が不可欠だった」

株式会社ベリサーブ品質保証部 技術フェロー佐々木方規さん
1985年CSK(現SCSK)に入社。組み込み機器からOS、グループウェア、データベースおよびデータベースデベロッパーソフトウェアなどのテスト実行/テストマネジメントを実施。1994年から開始したシステムテスト理論の研究を通じ、2004年にはテスト技術の研究開発/推進部門を設立し、R&D専任となる。品質マネジメント、ソフトウェア品質のコミュニティ活動やソフトウェア品質のキャリア人材育成などを主な責務として現在に至る。JSTQB認定テスト技術者資格 技術委員会 委員長、NPO法人ソフトウェアテスト技術者振興協会 理事、SQiP研究会 ODC分析研究会 運営委員会 委員長など。ソフトウェアテスト教科書 JSTQB Foundation 共著(翔泳社)、ソフトウェア不具合改善手法 ODC分析工程の「質」を可視化する 共著(日科技連出版)など。
目次
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。









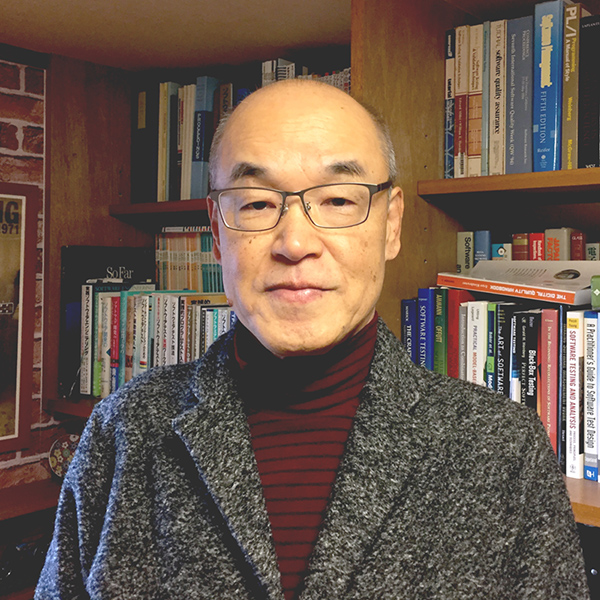






















.png)