ビジネス
【連載】QAの変遷を語る:ベリサーブ・江澤宏和さん「何をもってテストを終わりとすべきか」を問い続ける

株式会社ベリサーブ中部モビリティ第一事業部 技術部長江澤宏和さん
1992年、株式会社CSKに入社し、検証業務に従事。Windowsアプリケーションや組み込みソフトウェアの検証など幅広く経験。現在は、中部モビリティ第一事業部にて車載系ソフトウェアのプロジェクト支援を担当。
目次
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。





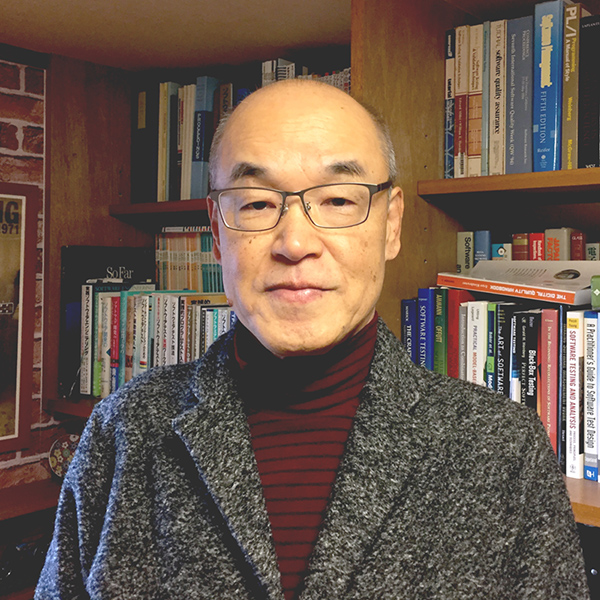

























.png)





























イノベーションを加速させる
おすすめ記事

日本企業はどう戦う!? 及川卓也さんが語るデジタル時代の道しるべ

経済産業省「DXレポート」の裏側、国がデジタルで目指す真の未来像とは?

セキュリティ専門家が指南:「危ない! 危ない!」というあおりに踊らされず、自組織の脆弱性を見極めた対処を SBテクノロジー・辻伸弘氏
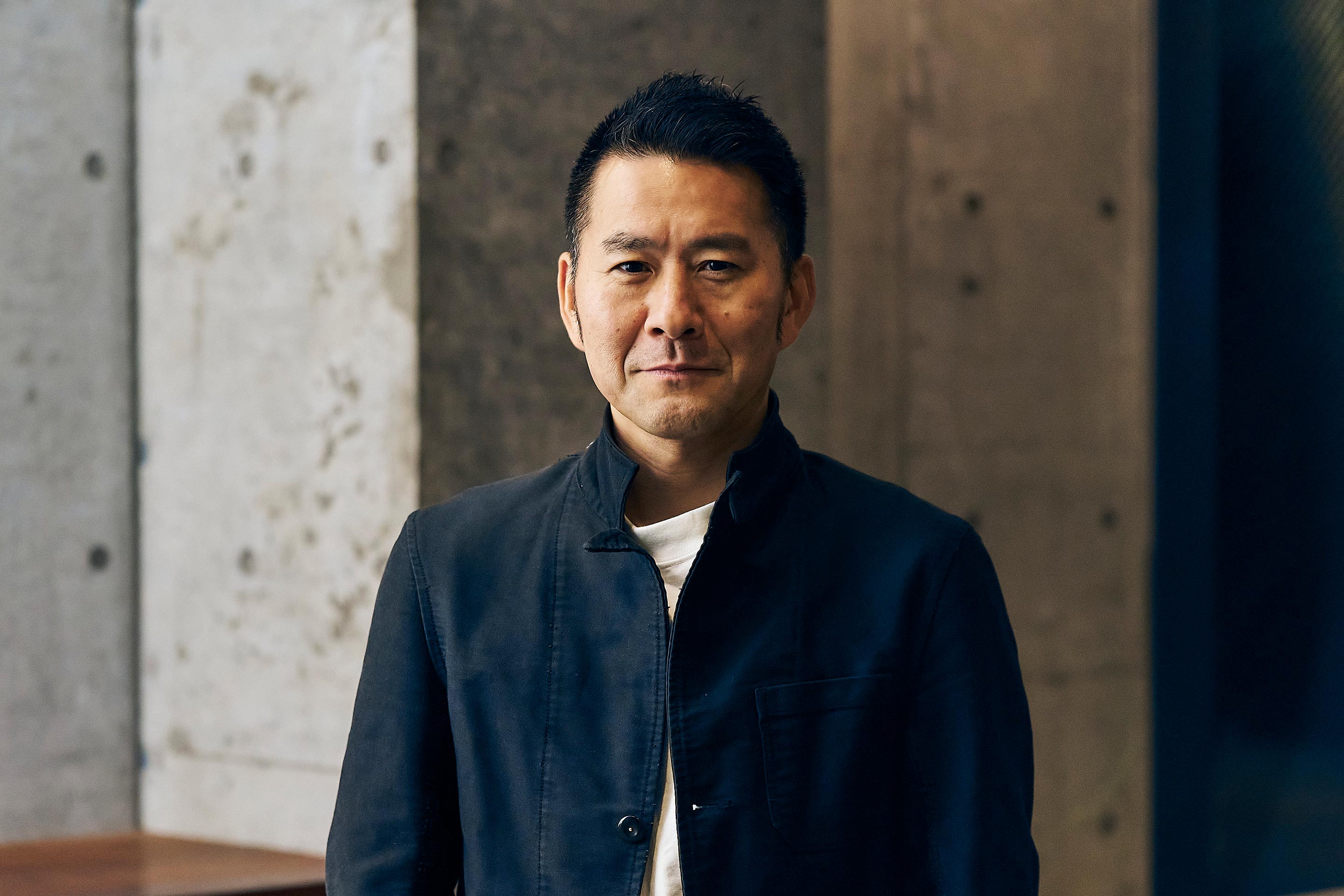
【連載】冒険者の地図:高卒エンジニアからメガベンチャーのリーダー職に、国内屈指のQAエンジニアに上り詰めた河野哲也さんの逆転人生(前編)
ランキング