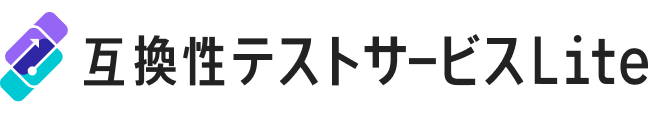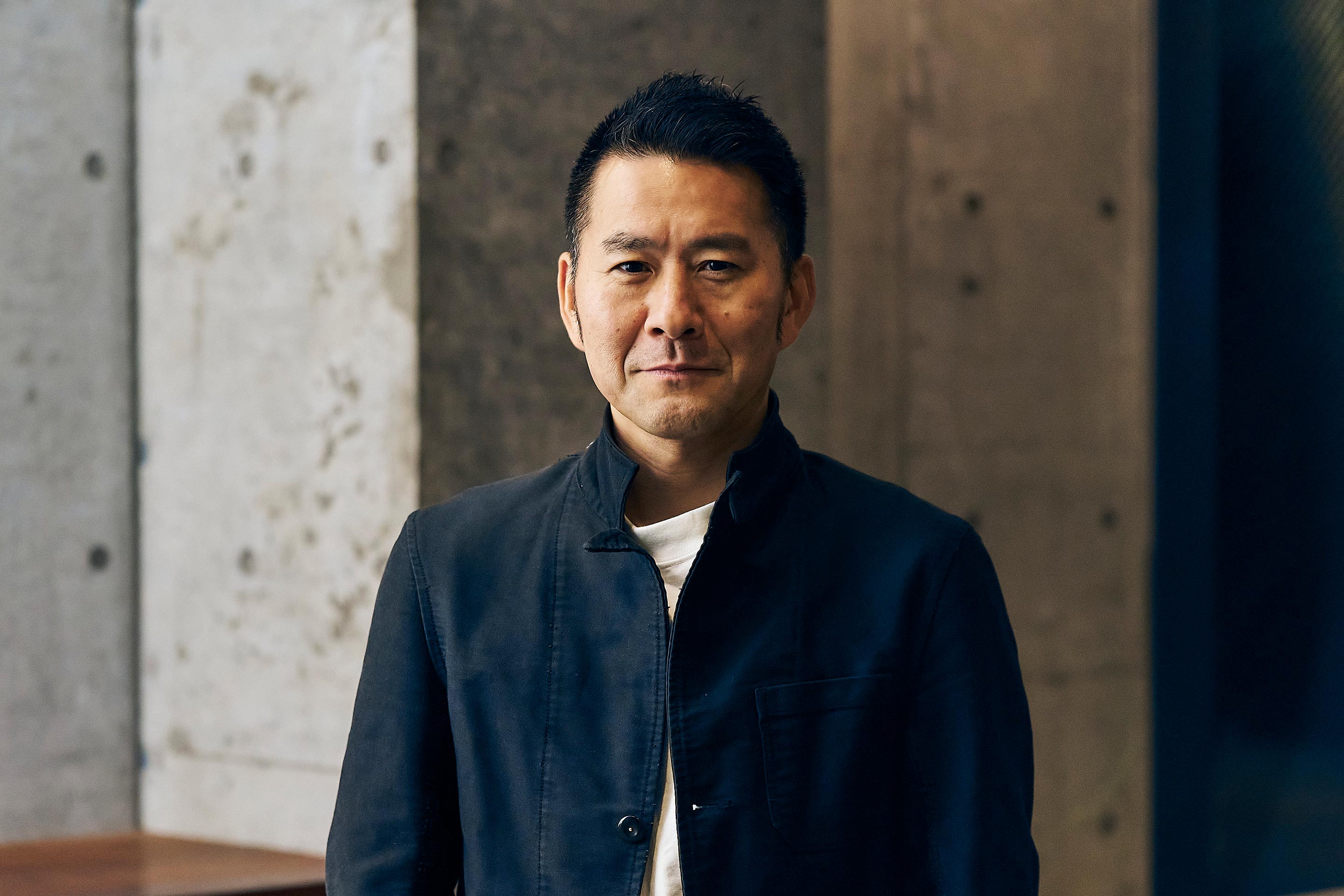ナレッジ
【連載】概念モデリングを習得しよう:圏Iのモデルを作ることと、人間が思考するということの関係性(第10回)
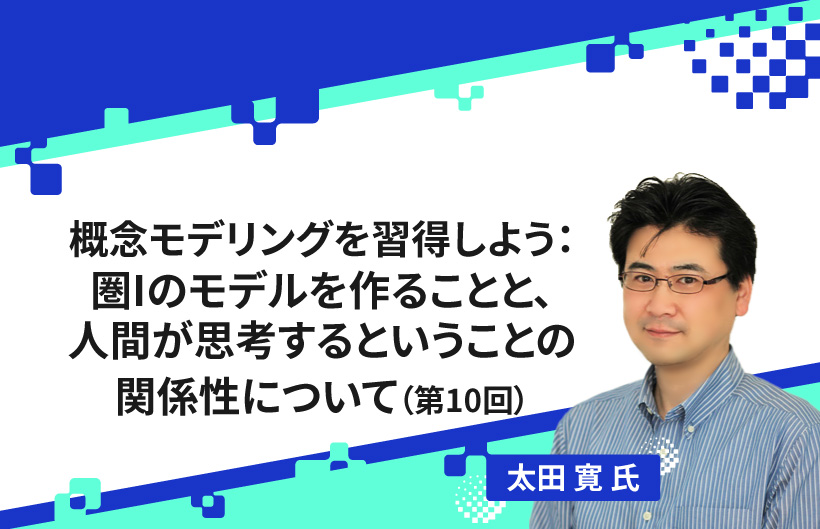
目次
【前回の連載記事はこちら】
【連載】概念モデリングにおける、二項リンクと関連リンク(第9回)
読者の皆さん、こんにちは。Knowledge & Experience 代表の太田 寛です。
この連載コラムでは概念モデリングの解説を行っています。今回は、圏Iのモデルを作ることと、人間が思考するということの関係性について言及します。
何度も繰り返しとなりますが、圏I のモデルは、モデル化対象の意味の場の写しです。意味の場を構成する存在を一つずつ拾い上げていくこと、それが圏I のモデルを作っていくことです。
拾い上げる存在は、
- 存在の性質 ⇒ 特徴値
- 個々の存在 ⇒ 概念インスタンス
- 存在間の意味的な関係 ⇒ リンク
です。
この過程は、圏論的な観点から、それぞれの圏(意味の場:圏S と圏I)の間の関手を定義しているとも言えます。意味の場から存在を拾い上げるという作業は、一つ一つ指さし(認識)しながら存在を数え上げていく作業であると捉えることもできます。
一方で、人間が意味の場を通じて観ている(あるいは感じている)物理的な現実世界は、連続的にダイナミックに変化する世界です。もしかするとプランク定数※より小さな極微では不連続な世界なのかもしれませんが、その世界は実質的に実数無限で構成されています。数え上げられる自然数もまた無限ですが、自然数の無限と、実数の無限では濃度が異なります。
※プランク定数は光の持つエネルギーの最小単位であり、この定数から電子1個の質量を導出することができる
少しだけ脇道にそれると、分数で表される有理数、√記号で表される無理数(これらは多項式の方程式の解になり得る数です)の数もまた、自然数と同じ数しかなく、自然数の無限の濃度と一致しています。無理数も自然数と同じように数え上げられるというのは驚きの事実ですね。実数はそれらに、円周率や自然対数の底などといった超越数が加わり、順番に数え上げる(つまり自然数無限)ことができない、より濃度の濃い無限になっています。
話を元に戻します。人間の思考のもとである言葉を使って紡いだ文章は自然数無限に過ぎません。“実数無限”という一つの単語を使ったとしても、それは実数無限なるものを切り取って言葉にしているだけで、実数無限な存在そのものを文章にすることはできません。概念モデリングによる圏I のモデル作成時の存在の拾い上げもまた、実数無限の対象を自然数無限に落とし込んでいる作業と言えます。
人間の思考とは、実数無限の対象を自然数無限に落とし込むことではないかと、筆者は考えています。実数無限の対象は、小説家・半村良の「妖星伝」風に言えば、“知る能(あた)わず(ナーマナナンダー)”なのではないでしょうか。
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。










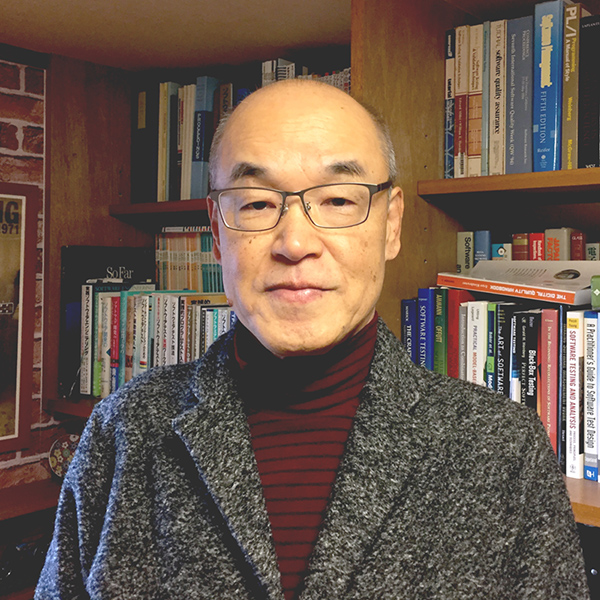





















.png)