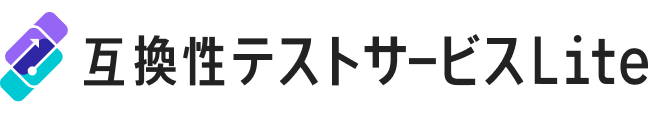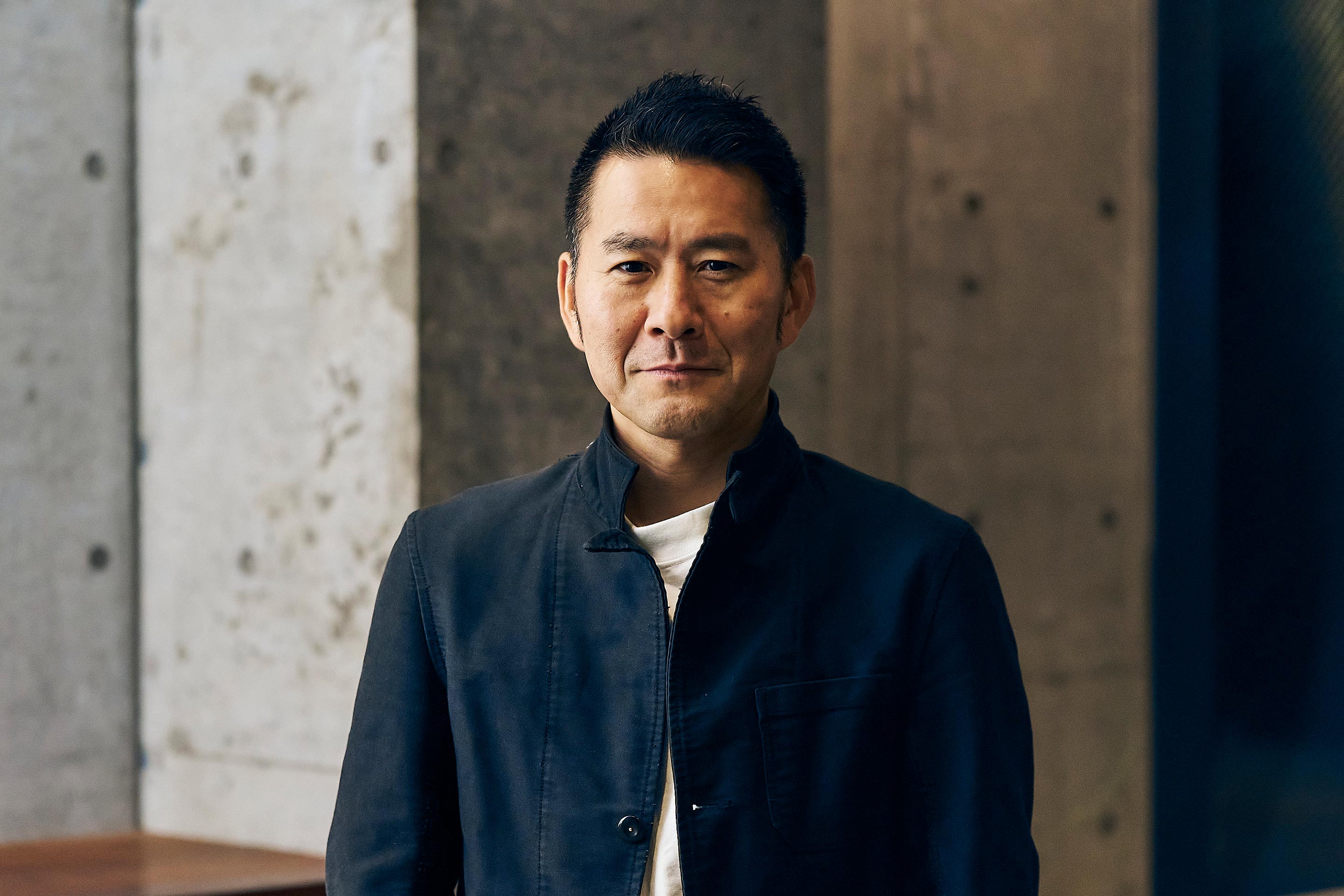ナレッジ
【連載】概念モデリングを習得しよう:圏Iのモデルにおける特徴値とリンク(第7回)
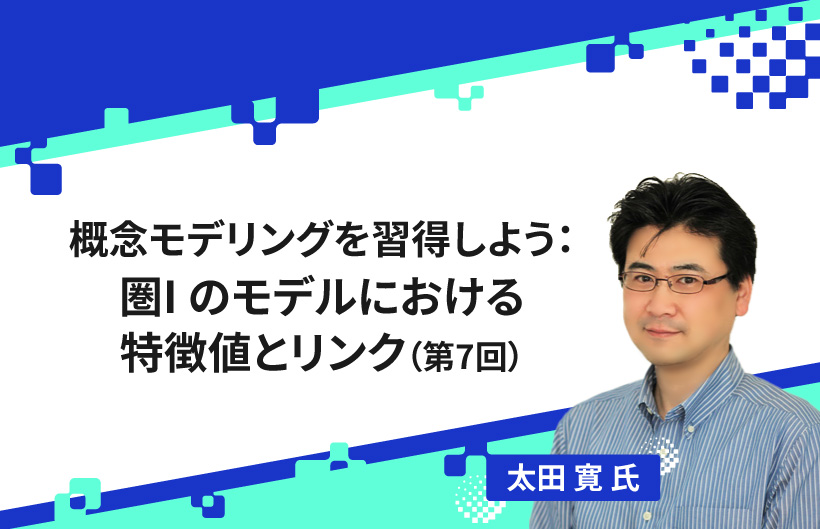
目次
【前回の連載記事はこちら】
【連載】概念モデリングを習得しよう:圏I のモデルによるシミュレーション(第6回)
読者の皆さん、こんにちは。Knowledge & Experience 代表の太田 寛です。
この連載コラムでは概念モデリングの解説を行っています。
前回は、概念インスタンス、特徴値、リンクを使って、モデル化対象の意味の場の状態を記述したモデルを、数学の基礎付けで活用されている圏論で精査し、圏Iのモデルと命名しました。
今回は、圏Iのモデルにおける、特徴値とリンクについて詳しく解説していきます。
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。










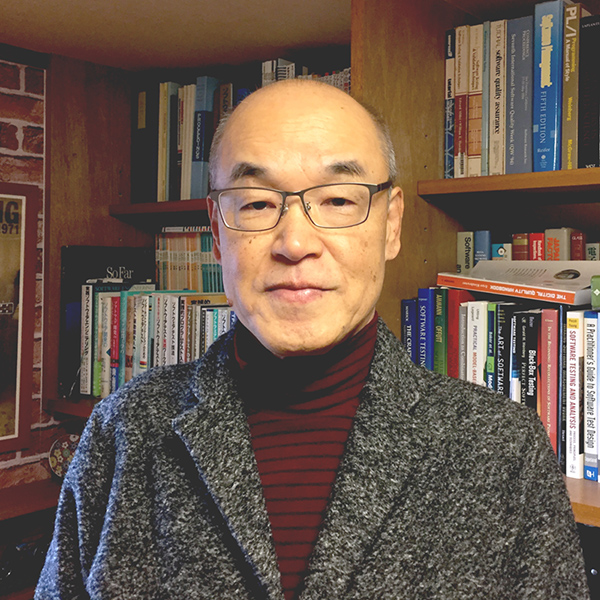





















.png)