ビジネス
【連載】第4回:ソフトウェアテストそもそも話~グラフを見たら網羅せよ!(前編)~
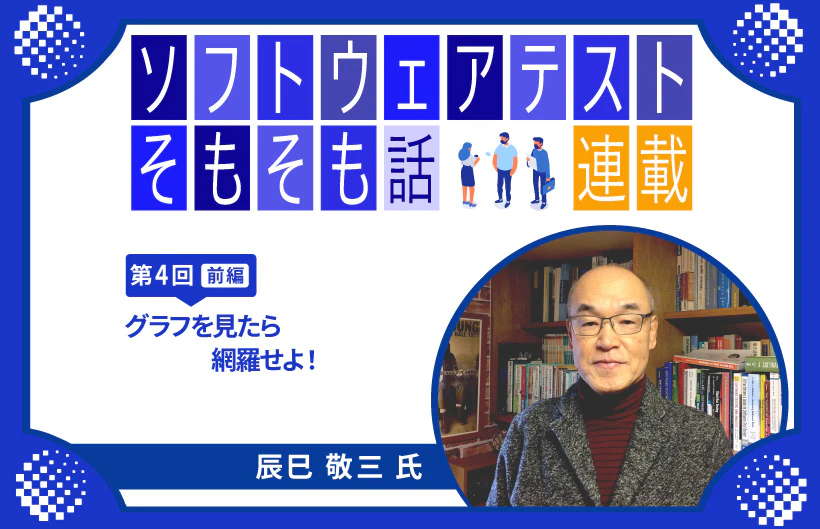
目次
「HQW!」の読者の皆さん、こんにちは。辰巳敬三です。
この連載コラムでは、ソフトウェアのテスト技術や品質技術の歴史を紹介しています。
前回は、「そも、デシジョンテーブルはテスト技法なのか」と題してデシジョンテーブルテストの歴史を解説しました。
今回は、制御フローテストを取り上げます。ところで、今回のサブタイトル「グラフを見たら網羅せよ!」が誰の言葉か、ご存じでしょうか?
これは、Boris Beizer(以下、Beizer)の著書『Software Testing Techniques, Second Edition』[1]に記されている言葉です。実際には、以下のように書かれています。
Question - What do you do when you see a graph?
Answer - COVER IT!
[翻訳本] 質問 - グラフを見たら、どうするか。
解答 - 網羅する!
このくだりは書籍中に二度登場し、さらによく似た表現も一カ所ありますので、Beizerのお気に入りのフレーズだったのかもしれません(お手元に書籍がある方は探してみてください)。
制御フローテストでは、処理の流れ(制御フロー)のグラフを描き、その経路を網羅することが基本的なアプローチとされています。では、「そもそも」誰が、いつ頃からコンピュータプログラムをグラフで表現し、網羅することを考え始めたのでしょうか?
なお、Beizerは前述の書籍の「第3章 フローグラフとパステスト法」において、制御フローに基づくテストを「パステスト法」と呼び、要点を次のように述べています。
パステスト法はテストの基礎であり、構造モデルとしてプログラムの制御フローを使うテスト法の一つである。本章では、プログラムの制御フローからテスト項目を生成する方法、パス選択の基準、特定のパスを実行するための入力データを決定する方法について述べる。
それでは、制御フローテストの歴史を、詳しく見ていきましょう。
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。












































-portrait.webp)
































