ビジネス
【連載】第4回:ソフトウェアテストそもそも話~グラフを見たら網羅せよ!(後編)~
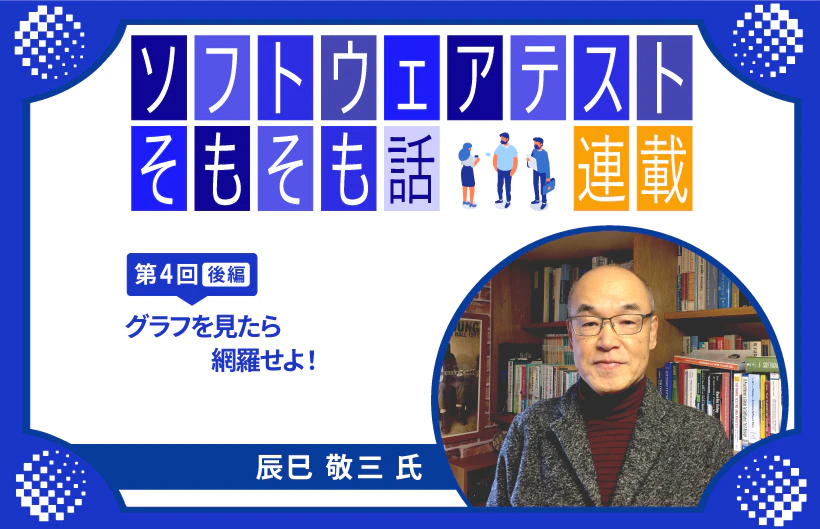
目次
「HQW!」の読者の皆さん、こんにちは。辰巳敬三です。
この連載コラムでは、ソフトウェアのテスト技術や品質技術の歴史を紹介しています。
第4回の前編では、プログラムの制御フローのグラフ化と解析、およびカバレッジの計測の歴史を解説しました。
後編では、カバレッジ計測システムとテストカバレッジ基準の歴史を解説します。
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。












































-portrait.webp)
































