ナレッジ
【連載】概念モデリングを習得しよう:概念情報モデルの活用(第15回)
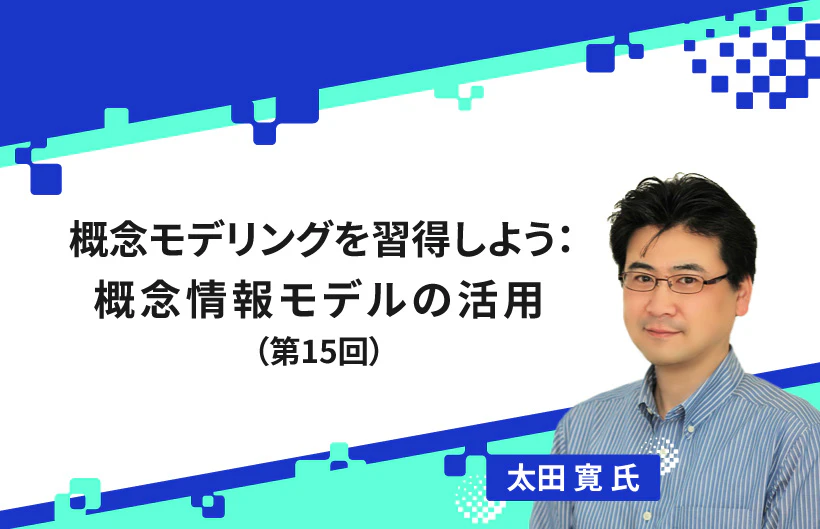
目次
【前回の連載記事はこちら】
【連載】概念モデリングを習得しよう:概念情報モデルと圏Iのモデルとの関係(第14回)
読者の皆さん、こんにちは。Knowledge & Experience 代表の太田 寛です。
この連載コラムでは概念モデリングの解説を行っています。
今回は、概念情報モデルの活用について解説します。
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。
ナレッジ
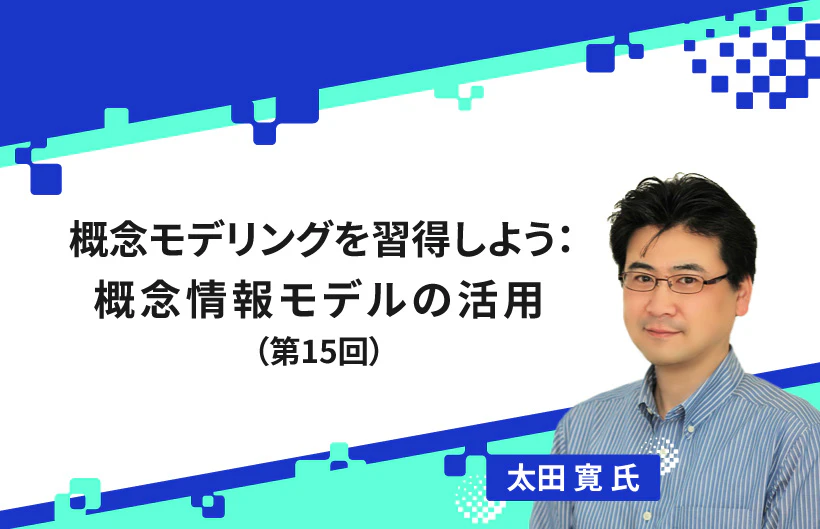
【前回の連載記事はこちら】
【連載】概念モデリングを習得しよう:概念情報モデルと圏Iのモデルとの関係(第14回)
読者の皆さん、こんにちは。Knowledge & Experience 代表の太田 寛です。
この連載コラムでは概念モデリングの解説を行っています。
今回は、概念情報モデルの活用について解説します。
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。











































-portrait.webp)



























イノベーションを加速させる
おすすめ記事

日本企業はどう戦う!? 及川卓也さんが語るデジタル時代の道しるべ

経済産業省「DXレポート」の裏側、国がデジタルで目指す真の未来像とは?

セキュリティ専門家が指南:「危ない! 危ない!」というあおりに踊らされず、自組織の脆弱性を見極めた対処を SBテクノロジー・辻伸弘氏

【連載】冒険者の地図:高卒エンジニアからメガベンチャーのリーダー職に、国内屈指のQAエンジニアに上り詰めた河野哲也さんの逆転人生(前編)
ランキング