ナレッジ
【連載】概念モデリングを習得しよう:概念情報を使った現実世界の参照と更新(第16回)
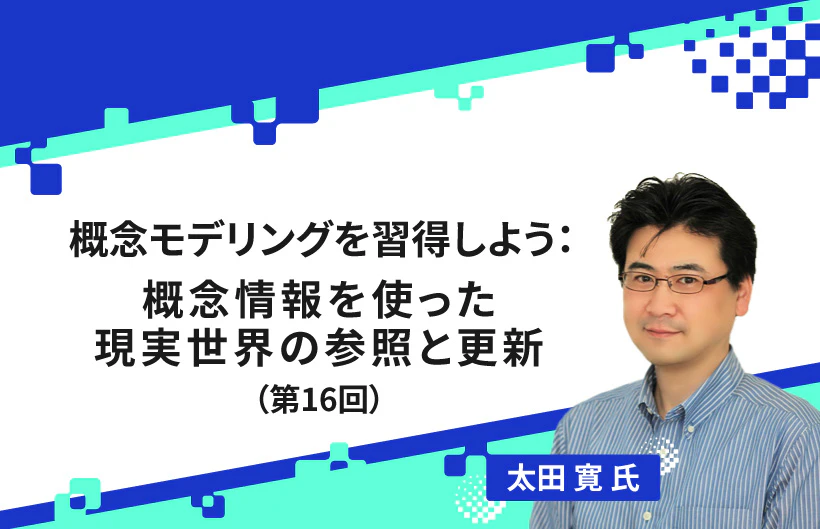
目次
【前回の連載記事はこちら】
【連載】概念モデリングを習得しよう:概念情報モデルの活用(第15回)
読者の皆さん、こんにちは。Knowledge & Experience 代表の太田 寛です。この連載コラムでは概念モデリングの解説を行っています。
今回から、概念情報モデルを使って、現実世界の参照・更新について解説していきます。
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。












































-portrait.webp)
































