スキルアップ
2025.11.12記事:林祥一
【連載】要求工学における「利用状況」の扱いをめぐる考察:要求(要件)定義に主語は必要か?(第4回①)
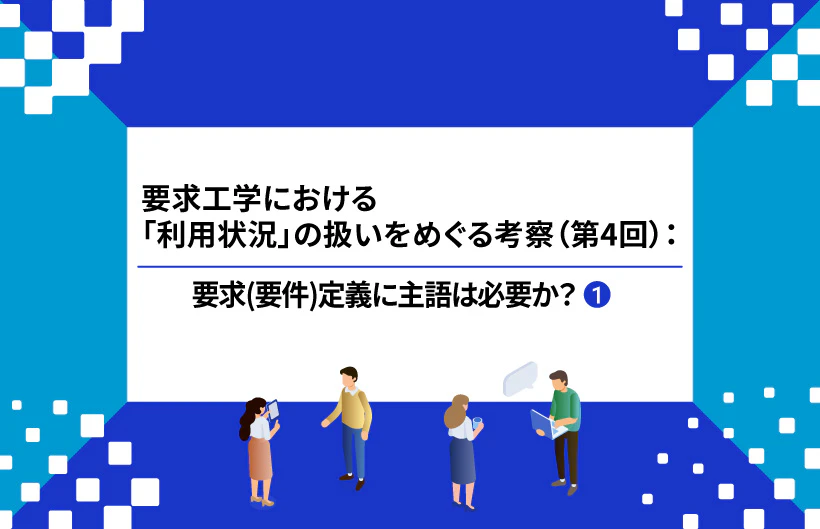
目次
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。
関連記事
- 【連載】要求工学における「利用状況」の扱いをめぐる考察:ジョブ理解に基づくマーケティングのインサイトを開発で確実に生かすには?(第1回)
- 【連載】要求工学における「利用状況」の扱いをめぐる考察:SQuaREの「利用時の品質モデル」から「利用状況網羅性」はなぜ消えた?(第2回)
- 【連載】要求工学における「利用状況」の扱いをめぐる考察:アジャイルにもウォーターフォールにも効果的! 振る舞い駆動開発(BDD: Behavior Driven Development)のプラクティス(第3回①)
- 【連載】要求工学における「利用状況」の扱いをめぐる考察:アジャイルにもウォーターフォールにも効果的! 振る舞い駆動開発(BDD: Behavior Driven Development)のプラクティス(第3回②)
- 【連載】要求工学における「利用状況」の扱いをめぐる考察:アジャイルにもウォーターフォールにも効果的! 振る舞い駆動開発(BDD: Behavior Driven Development)のプラクティス(第3回③)
この記事を書いた人

執筆
林祥一
株式会社ベリサーブ ソフトウエア品質コンサルティング部。 1989年、NTTソフトウェア入社。交換機の性能検証、情報資源辞書システム(IRDS)の開発に従事。1991年、富士ゼロックスのシステム技術研究所に入所。オブジェクト指向言語拡張によるマルチエージェントシステム, CSCWの研究に従事。1998年に試作システム商品化のため開発部門に異動。以降、文書/記録管理・コラボレーション支援・ワークフロー・内部統制・エンタープライズリスク管理などのプラットフォーム開発のアーキテクトおよび商品企画に従事。また一時期、iDCの運用設計にも従事。2010年にHAYST法をお客様に伝授する役目を担ったことをきっかけに、コンサルティング活動を開始。2018年ベリサーブ入社。 ※執筆者の所属、肩書などは執筆当時のものです。











































-portrait.webp)
































