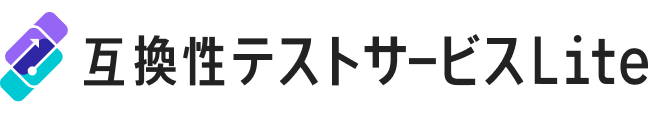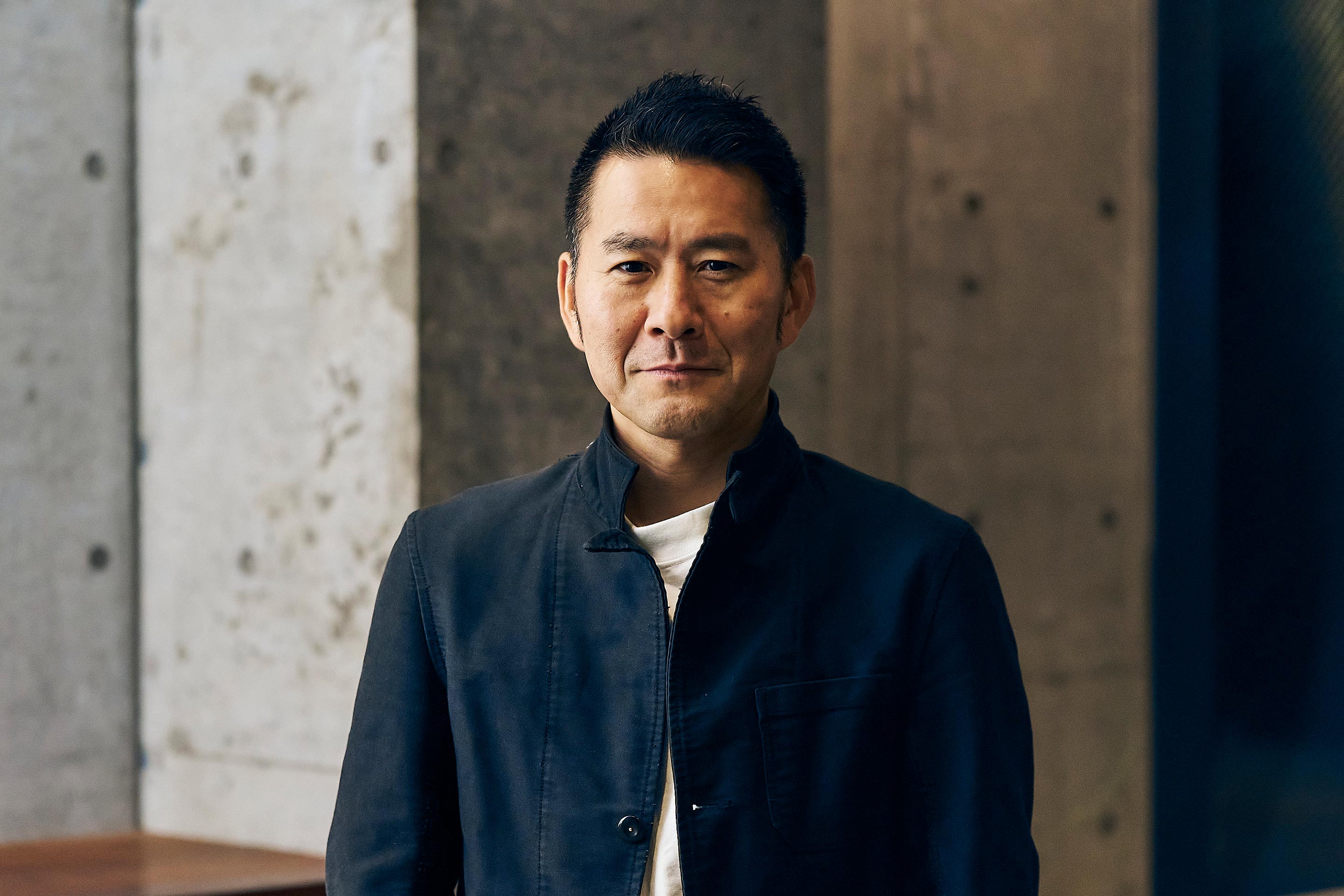ナレッジ
SBOMとは?導入メリットや標準フォーマット、種類を解説
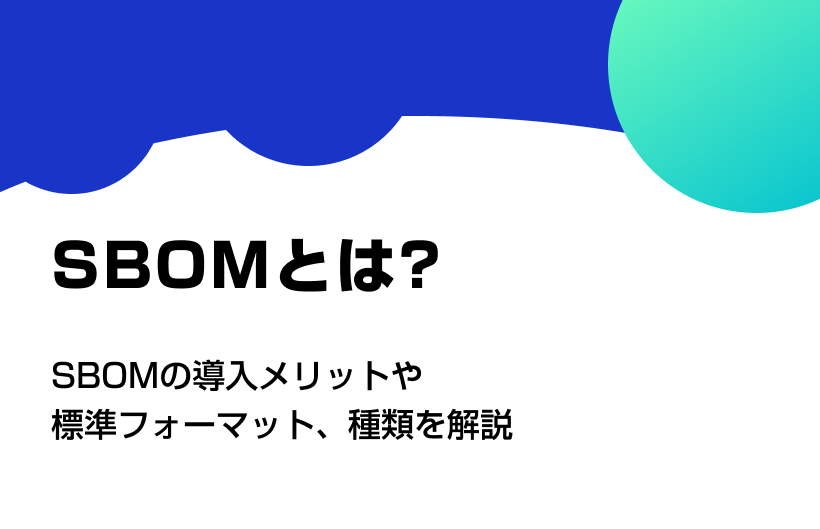
この人に聞きました:株式会社ベリサーブ サイバーセキュリティ事業部 マーケティング部長武田一城さん
株式会社ベリサーブ サイバーセキュリティ事業部 マーケティング部長。1998年に大学を卒業。2000年問題対応の真っ最中にIT業界に入り、インターネットビジネス草創期から新事業のマーケティング戦略立案と実行の経験を積む。その結果、システム基盤とセキュリティ分野におけるマーケティングスペシャリストとなる。これまでに製品・サービスの新規立ち上げの実績を数多く経験。特に、日本での次世代型ファイアウォール市場立ち上げで大きな成果を出した。web、雑誌、学会誌、書籍等の執筆実績も多数。一般の人にも分かりやすいセキュリティの解説などで定評がある。日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)や情報処理推進機構(IPA)、日本シーサート協議会(NCA)、日本PostgreSQLユーザ会等の組織においてWG活動や委員、理事を歴任。
目次
サイバーセキュリティが企業活動の重要課題となる中、ソフトウェア管理の透明性を高めることから注目を集めている「SBOM」。SBOMは、製品やシステムに使用されるソフトウェアを一覧化した情報であり、脆弱性やライセンスのリスクを明確にする手段として期待されています。
本記事では、SBOMの基本的な役割や標準フォーマット、関連ツールの特徴、導入に際して直面する課題とその対策を解説します。今回は、サイバーセキュリティ事業部 マーケティング部長の武田一城さんのお話や寄稿物(※1)を基にHQW!編集部でまとめました。SBOMが企業のセキュリティ強化やソフトウェア管理の効率化にどのように貢献できるのか、理解を深めるきっかけとしてご活用ください。
SBOMとは?
SBOM(Software Bill of Materials:ソフトウェア部品表)は、製品やシステムに使用されている全てのソフトウェアのリストを指します。サプライチェーンにおける透明性を高めるために作成されるもので、特にオープンソースソフトウェア(OSS)のライセンス管理や脆弱性対応において重要な役割を果たします。
経済産業省のガイドラインでは、SBOMを以下のように定義しています。
「ソフトウェアコンポーネントやそれらの依存関係の情報も含めた機械処理可能な一覧リスト」(※2)
つまり、SBOMにはソフトウェアに含まれるコンポーネントの名称、バージョン情報、開発者の情報が含まれ、OSSだけでなく自ら開発したプロプライエタリソフトウェアに関する情報も対象にします。
また、SBOMをサプライチェーン上で相互共有することで「ソフトウェアサプライチェーンの透明性を高めることが期待されており、特に、コンポーネントの脆弱性管理の課題に対する一つの解決策として期待されている」としています。(※2)
注目される契機は、2021年に発行された米国大統領令「国家のサイバーセキュリティの向上に関する大統領令」で、SBOMがサイバーセキュリティ対策の鍵として取り上げられたことです。また、EUサイバーレジリエンス法(CRA :EU Cyber Resilience Act)(2022年草案、2025年後半適用予定)もSBOMの重要性を強調し、特に製造業や重要インフラ管理における利用を促進しています。
参考:ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引 ver 2.0|経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課
経済産業省のガイドラインに基づくSBOMのメリット
経済産業省のガイドライン「SBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引 ver2.0」によれば、SBOMの導入により図表1のようなメリットが得られるとされています。(※2)
脆弱性管理 | ・SBOMを利用して脆弱性情報を収集し、対象ソフトウェアに含まれるコンポーネントの影響有無を迅速に判断できる |
|---|---|
ライセンス管理 | ・SBOMによってコンポーネントのライセンス情報が明確化され、ライセンス違反リスクを低減できる |
開発生産性向上 | ・開発の初期段階からSBOMを活用することで、コンポーネントに含まれる既知の問題を早期に発見できる |
図表1:SBOM導入の主なメリット
SBOMを活用することで、ソフトウェアのEOL(End-of-Life)管理が容易になるなど、その他の管理メリットもあるとされています。これらの利点は、ソフトウェア管理の効率化だけでなく、企業全体の競争力向上にもつながるとされます。
SBOMの標準フォーマットと主要形式
SBOMの標準フォーマットには、以下のような主要な形式が含まれます(図表2)。
SPDX(Software Package Data Exchange) | 主にOSSのライセンス情報を含むフォーマット |
|---|---|
CycloneDX | セキュリティ関連の情報を重視したフォーマット |
SWID(Software Identification Tags) | ソフトウェアのライセンスやインベントリ管理に特化した形式 |
図表2:SBOMの標準フォーマット
経済産業省のガイドラインでは、これらのフォーマットについて「機械判読可能かつ相互運用可能なフォーマットを用いて作成され、共有される」ことが重要と述べられており、SPDX、CycloneDX、SWIDタグを推奨しています。(※2)
これらの標準フォーマットを利用することで、SBOMを用いたソフトウェア管理の効率化やセキュリティの向上が期待されています。
SBOMツールの種類
SBOM管理に活用されるツールには、以下のようなタイプがあります(図表3)。
OSS管理ツール | OSSのライセンスおよび脆弱性を管理するためのツール |
|---|---|
脆弱性スキャナー | OSSの脆弱性を検出するスキャナー機能を持つツール |
SBOM作成支援ツール | ソフトウェア部品表を自動的に生成し、可視化するためのツール |
図表3:SBOMツールの種類(タイプ)
SBOMを利用して脆弱性の迅速な特定、ライセンス管理の効率化、および依存関係の把握を行うことが可能です。
SBOMとセキュリティ上の課題・対策
SBOMの導入に関する課題と対策について紹介します。
課題
- ツールのコスト
- ノウハウ不足
- リソース不足
対策
- 自動化の推進
- コスト削減
SBOMの普及において、最初に直面する課題は「ツールのコスト」です。OSS管理ツールは高額であり、多くの企業が導入に踏み切れない状況が続いています。これが特に中小企業の普及を妨げる大きな要因です。
「ノウハウ不足」も課題の一つです。製造業の設計・開発部門では部品表管理が一般的である一方で、情報システム部門などではSBOM運用の経験や知識が乏しいことが大きな障壁となっています。また、「リソース不足」によって脆弱性対応に必要な人員や時間が足りず、結果として対応が遅れるケースが多発しています。
これらの課題を解決するための対策として、「自動化の推進」が挙げられます。SBOMを活用して脆弱性管理を自動化することで、人的リソースの負担を大幅に軽減できます。また、「コスト削減」はSBOMの普及に欠かせない要素です。そのため、ツールの導入コストを抑える政策や支援の実施が求められており、より多くの企業が導入しやすい環境を官民一体となって整備することが重要です。
SBOMの導入・運用の実務と管理手法
SBOMの導入は、自動車業界や医療機器業界などで進んでいます。
自動車業界 | 業界団体であるJ-Auto-ISACがガイドラインを策定し、共通のSBOM運用を推進 |
|---|---|
医療機器業界 | 厚生労働省が策定した「医療機器のサイバーセキュリティ手引書」においてSBOMの利用を推奨 |
SBOM運用では、企業ごとの事情に適した管理フレームワークの選択が重要と言えるでしょう。
SBOM関連サービス・製品の動向と選定ポイント
SBOM関連のツールやサービスは、ソフトウェア管理の効率化やセキュリティ強化を支える存在として進化を続けています。その多様化に伴い、選定や運用における課題も明らかになってきました。
サービス・製品の動向
経済産業省のガイドラインによると、近年、SBOM関連ツールやサービスは多様化し、以下のような特徴や課題が見られます。
- ツールの進化
- 無償ツールの課題
- 相互運用性の不足
SBOMツールは、「SBOMの作成、共有、活用、管理を可能にする」総合的なツールとして進化しています。有償のSBOMツールでは、OSSの依存関係や再帰的な利用(再利用部品)も効率的に検出・管理できる機能が備わっており、さらに、ライセンス情報の可視化や注意が必要なライセンスへの警告表示機能など、コンプライアンス遵守をサポートする機能が充実しています。
一方、無償ツールには「環境整備や学習に必要な情報が不足している」「再帰的な部品の検出が十分でない」などの課題が指摘されています。加えて、取扱い可能なフォーマットが限定されていることや、ライセンス情報の検知漏れが発生する場合もあるため、利用時には注意が必要です。
また、現状では異なるSBOMツール間で生成されたSBOMの相互共有が難しく、普及の障壁となっています。この点については、国際的な標準化とツール開発の調和が求められています。
選定ポイント
SBOM関連ツールやサービスを選定する際には、以下のポイントが重要です。
SBOMツールを選定する際には、まず「導入コスト」を慎重に検討する必要があります。有償ツールの場合、初期投資が発生しますが、その費用が管理工数の削減効果とバランスが取れるかを十分に検討し、評価することが重要です。
「機能の充実度」にも目を向けましょう。SBOMの作成、管理、分析を包括的にサポートするツールが理想的であり、特に脆弱性管理やライセンス管理に特化した機能が備わっていることが求められます。
「運用の容易さ」も重要な選定基準です。ツールが直感的で使いやすいか、専門知識が乏しいチームでもスムーズに運用できるかを確認してください。さらに、サポート体制が充実しているツールを選ぶことで、導入後のトラブルにも迅速に対応でき、運用がより円滑になります。
「相互運用性」も欠かせないポイントです。異なるSBOMツールで生成されたSBOMを問題なく共有できることは、サプライチェーン全体の情報連携をスムーズにし、効率的な管理を実現する上で大きな利点となります。
SBOMの導入は長く効率的に運用できる手法を
ここまで、SBOMとは何かというところから、各業界の動向や導入に当たってのポイントまで解説してきました。
今後もSBOMは、導入が進んでいる自動車業界や医療/医療機器業界にとどまらず、遅かれ早かれ各業界で広がりを見せていくでしょう。SBOMの導入は企業にとってのゴールではなく、その効率的な運用の仕組みを整備し、継続していくことが非常に重要です。
当社は10年以上のSBOMの取りまとめや運用実績を持っている企業です。また、40年以上のテスト分野の専門知識によって、お客様に安心して利用できるサービスをご提供しております。ぜひお問い合わせください。
■関連サービス■
■参考文献■
(※1)日本セキュリティ・マネジメント学会誌「産業界におけるSBOM の現状」武田 一城
(※2)経済産業省「SBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引 ver2.0」

この人に聞きました:株式会社ベリサーブ サイバーセキュリティ事業部 マーケティング部長武田一城さん
株式会社ベリサーブ サイバーセキュリティ事業部 マーケティング部長。1998年に大学を卒業。2000年問題対応の真っ最中にIT業界に入り、インターネットビジネス草創期から新事業のマーケティング戦略立案と実行の経験を積む。その結果、システム基盤とセキュリティ分野におけるマーケティングスペシャリストとなる。これまでに製品・サービスの新規立ち上げの実績を数多く経験。特に、日本での次世代型ファイアウォール市場立ち上げで大きな成果を出した。web、雑誌、学会誌、書籍等の執筆実績も多数。一般の人にも分かりやすいセキュリティの解説などで定評がある。日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)や情報処理推進機構(IPA)、日本シーサート協議会(NCA)、日本PostgreSQLユーザ会等の組織においてWG活動や委員、理事を歴任。
この記事は面白かったですか?
今後の改善の参考にさせていただきます!
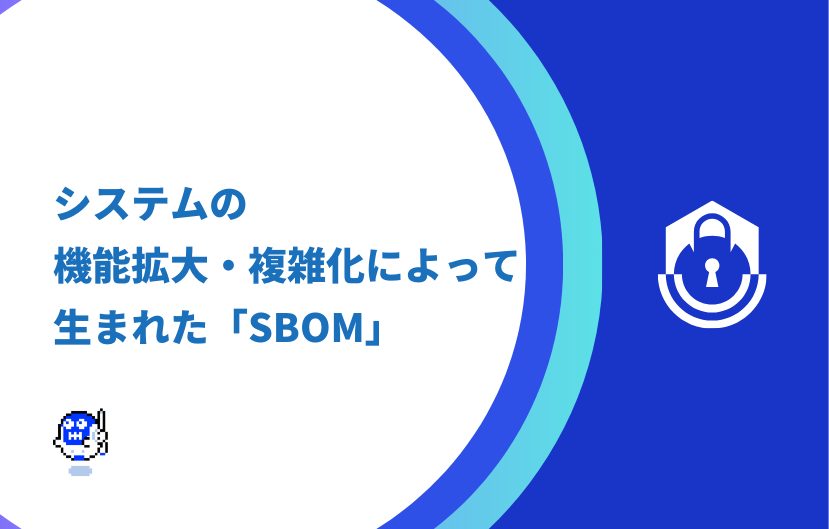





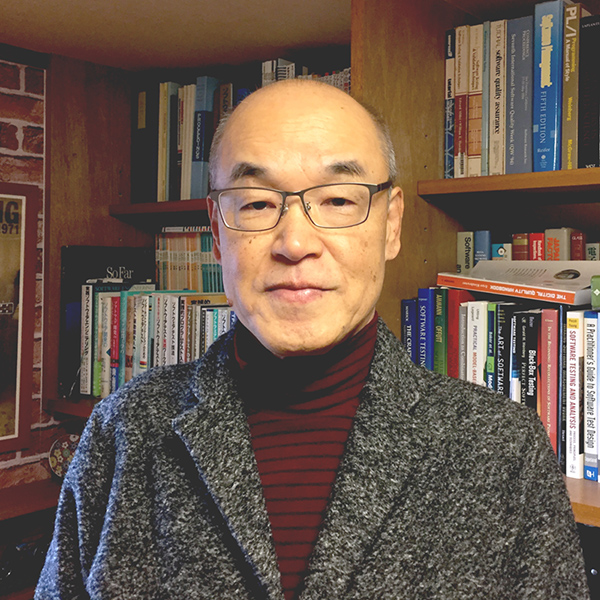


























.png)