ビジネス
2025.09.12記事:杉崎眞弘
【連載】ODC分析についてのよもやま話〜ソフトウェア不具合についてのあれやこれや・・・〜第1回:ソフトウェア開発の見える化とは?
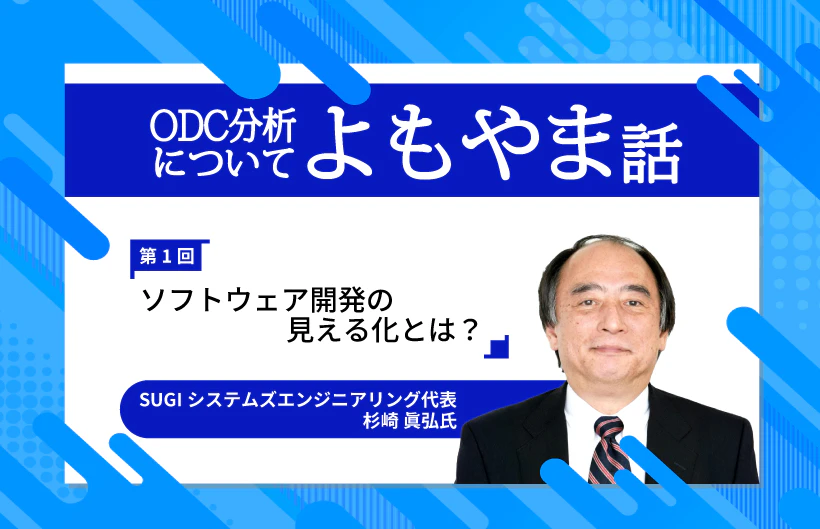
目次
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。
この記事を書いた人

執筆
杉崎眞弘
SUGIシステムズエンジニアリング代表、(株)ベリサーブ コンサルティング部 顧問、日本科学技術連盟ODC分析研究会 運営委員。長年日本I B M株式会社 研究開発部門にて、中小型システム、THINKPAD、組み込みシステムのOSや通信ソフトウェアなどを担当する品質保証部門長を歴任し、加えて海外IBM研究所と連携して品質検証技術、開発プロセス改革技術の導入・展開を主導。特にODC分析、DPP (Defect Prevention Process)などを固有技術として社内講師として普及に務める。後年、社内で蓄積してきた開発技術を社外に提供する研究所発のコンサルティング事業部を立ち上げ、多数の技術コンサルタントを育成し、国内企業への開発技術、品質検証技術また開発プロセス改革の技術支援を実施。現在、コンサルティング事業の傍ら、日本科学技術連盟ODC分析研究会運営委員として定例「ODC分析基礎セミナー」の講師を務めている。また(株)ベリサーブのコンサルティング部の顧問として、コンサルティング・ビジネスの拡大を支援している。著作に「ソフトウェア不具合改善⼿法ODC分析」 〜 ⼯程の「質」を可視化する 〜、⽇科技連ODC分析研究会編 杉崎眞弘・佐々⽊⽅規、株式会社日科技連出版社 (ISBN978-4-8171-9713-9)など。











































-portrait.webp)
































