ビジネス
【連載】ODC分析についてのよもやま話〜ソフトウェア不具合についてのあれやこれや・・・〜第2回「ソフトウェア不具合についての3つの気づき」(1)
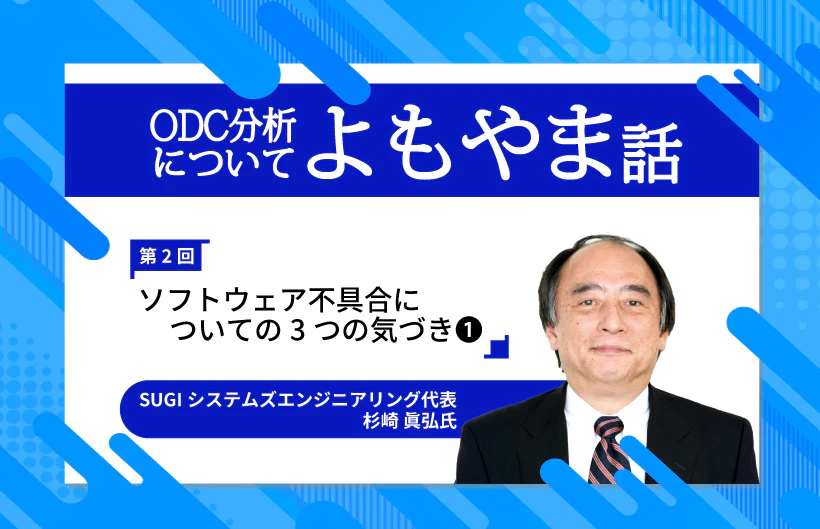
目次
読者のみなさん、こんにちは。杉崎眞弘です。
この連載コラムでは「ODC分析についてのよもやま話」と題して、ODC分析にまつわる不具合についての味わい方、開発プロセスの志の再認識、さらにソフトウェア品質についての考え方や捉え方にまで話を広げて、あれやこれや「よもやま話」としてお伝えしています。
この記事は会員限定です。新規登録からベリサーブIDを取得すると
続きをお読みいただけます。












































-portrait.webp)
































